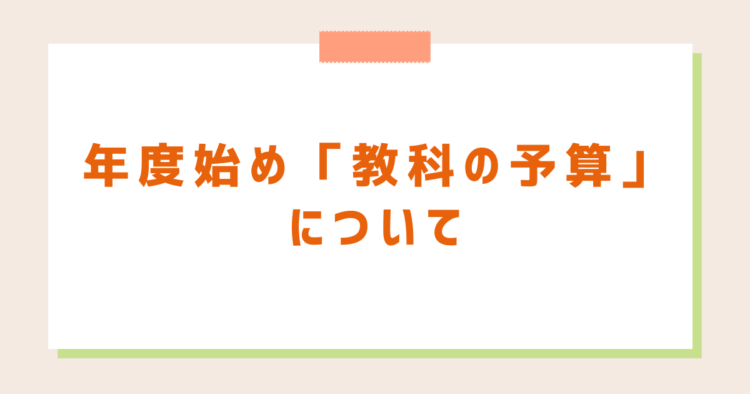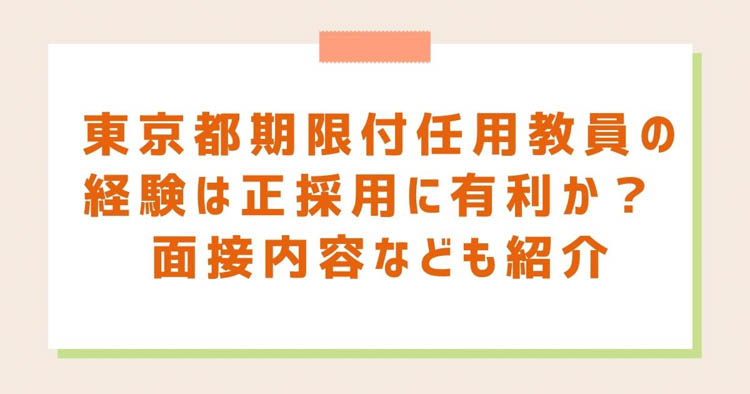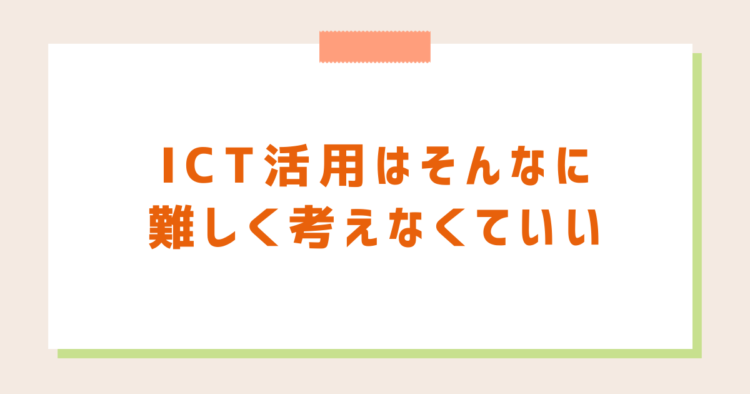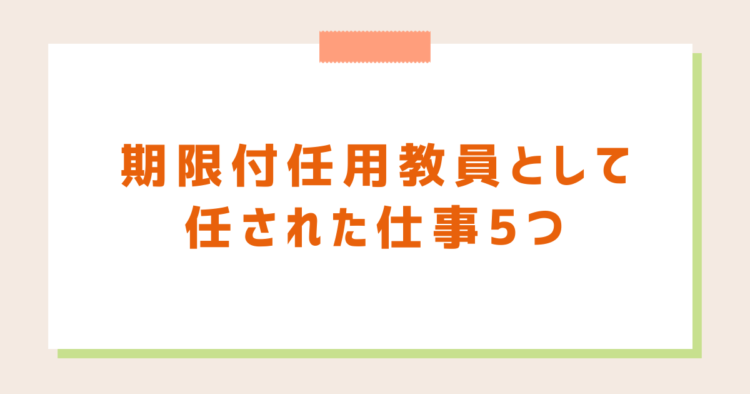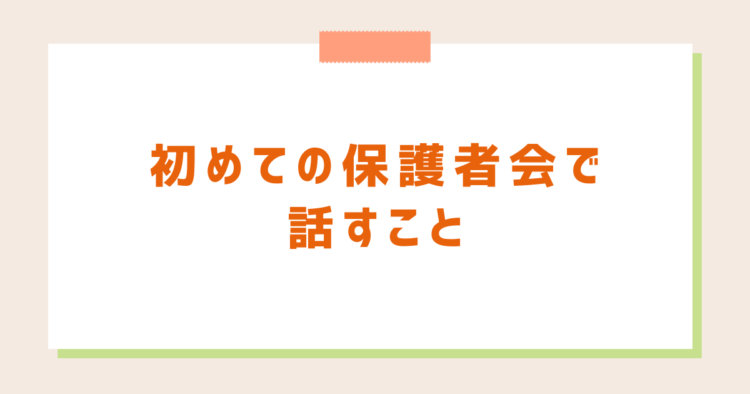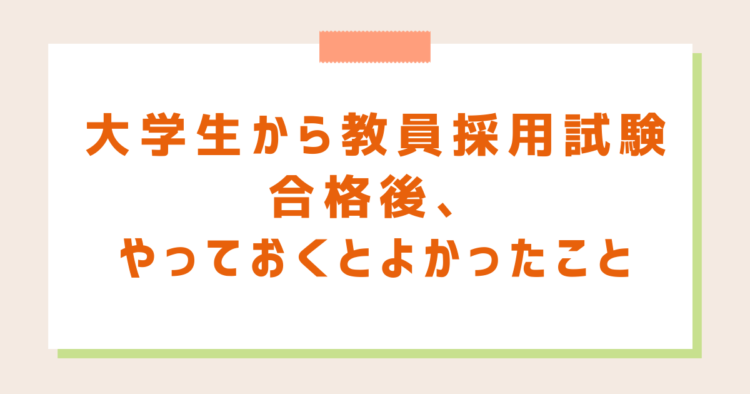定期テストを作るときに気をつける5つのポイント

生徒にとってもテストは嬉しいものではないですが、教員にとってもテストって嫌ですよね。
今回は、定期テストを作るときに、私が心がけていたことを書いてみたいと思います。
教科によるテストの位置付けを見極める
教科によって、テストの位置付けや負担はけっこうちがいます。
そもそも実技教科なら、実技や作品の評価もあるので、ペーパーテストは年に3回しかないですし、1回のテストの量や負担も教科によってちがいます。
実技教科でも美術の先生はカラーで図版を入れたりと、大変そうでした。
自分の教科でどのくらいペーパーテストが重要なのか、今までの先生はどのくらいの問題を出していたのか、まずは過去問などを見て現状を把握しましょう。
その学校・学年の学力レベルを把握する
初めての学校に着任したとき、その学校、学年ごとの平均的なレベルを把握しておくことは大事です。
同じ市町村でも、地域や学校によって、さらには学年によって学力がちがいます。
ここを把握していないと、平均点が80点超とか、平均点が40点というようなことが起こってしまいます。
2年生、3年生なら学年の先生方に事前にレベル感を聞いておくのが安心です。
1年生の場合も、小学校からの情報を他の先生方と共有したりして、とりあえず他教科とレベル感を合わせるように作成するといいと思います。
採点のことを考えて問題を作成する
これが最も重要なことですが、作りたい問題をやみくもに作るのではなく、採点のことを見据えて問題作成します。
問題用紙、採点用紙の枚数と大きさ
問題用紙や解答用紙の枚数や大きさを考えるのは、作問者自身のためと、試験監督の先生の負担を減らすためでもあります。
教科によって、どうしても問題用紙が増えてしまう場合もあると思いますが、生徒が見にくく不便にならない程度に、両面印刷にしたり、問題用紙のサイズを調整します。
例えば、問題用紙がA4で4枚なら、A3両面印刷で1枚に収めることができます。
さらに、A3サイズのままだと大きくて印刷後の保管や、試験の配布のときに扱いづらいので、折り機があればそれにかけて2つ折りのA4サイズにしておきます。
また、解答用紙は問題用紙とは別に考えます。採点の時に扱いやすいサイズにします。
個人的には記号回答や短い記述での回答が多い教科は、B5またはA4サイズがいいと思います。採点の時に大きい紙はめくりにくいからです。
ただし、国語や英語など記述量がが多い教科は小さくすると生徒が書き込みにくいし、採点する側も読みにくくなるので大きい方がストレスが減りそうです。
私は担当が家庭科だったのですが、中学校では技術・家庭科で1つの教科でした。
試験時間が同時だったので、技術の先生と話し合って、問題用紙はそれぞれが作り、解答用紙は印刷時に1枚に合わせてB4などのサイズで印刷し、試験後、解答用紙を回収した後に裁断機で半分にしてそれぞれ採点していました。
この方法は、試験管を担当してくださる先生方から、配布が楽だとすごく好評でした。
問題、解答の形式
問題、解答の形式というのは、記号式や記述式などです。
これは、テストの難易度と、採点のしやすさに直結します。
記号問題のいいところは、とにかく採点がしやすいことです。
記号にしたら簡単になりそうと思うかもしれませんが、選択肢の数や内容、数択なのかマルバツ問題にするのか、などいろいろな難易度にできます。
記述問題は、教科によりますが、できるだけ記述でも答えが1つになるような問いにします。例えば、法律の名前が答えになるような問題や、どうしてそうなるか物事の機序を問うような問題であれば、答えを知っているか知らないかなので解答が1つになりやすいです。
(国語の先生はこのやり方はさすがに難しいと思うので、いつもテストにかかる労力がすごそうで、尊敬します…)
そして、複数回答はできるだけ避けるというのもおすすめです。
順不同で解答が複数ある場合は、採点の際の頭のメモリーが余計に必要になり、スピードが落ちるだけでなくミスが増えてしまいます。
問題数と配点
問題数と配点は、バランスが大切です。
個人的には、家庭科で50点満点だったので、1問1点で丸の数=合計点、としたこともあって、それはそれでやりやすかったです。
ただし、大半の教科は100点満点なので、1人につき100個丸をつけると考えると、腱鞘炎になりそうだなと思います。
この場合は、2点とか5点とか配点の大きい問題も混ぜることで、問題数を減らすことができます。私も100点満点のテストを作るとしたら2点問題は積極的に入れると思います。
ここで重要なのが、配点のバリエーションをできるだけ減らすことです。
どういうことかというと、例えば100点の内訳が、
1点問題が11問(11点)、2点問題が20問(40点)、3点問題が5問(15点)、5点問題が4問(20点)、7点問題が2問(14点)という場合と、
1点問題が20問(20点)、2点問題が20問(40点)、5点問題が8問(40点)という場合だと、
前者の方が採点が簡単になります。
採点してみるとわかりますが、問題用紙に赤丸をつけていくと、紙面が散らかった感じになって、最後に点数を数える時にはけっこう頭を使います。電卓を使ったとしても、元が複雑な構成になっていると大変です。
そのため、元々の配点や構成(同じ配点の問題は近くにまとめておくなど)にしておくことで、負担を減らすことができます。
成績をつけることを考えて問題を作成する
その問題が、評価項目のどの項目に相当するのか、初めから想定して、そのバランスを見ながら問題を作ります。
これはベテランの先生にとって当たり前かもしれませんが、私は当初、とにかくテストを形にすることで精一杯で、成績をつける頃になって、あ、この評価項目をテストでもっと入れておけば良かったなと思うことがありました。
感心意欲態度など、どうしてもテストで測ることが難しめな項目もありますが、実技や授業での取り組みなど他の評価材料とも合わせて、成績をつける時に困らないくらいの評価をテストでするように考えると、後から楽になります。
作りやすいソフトを見つけ、データは蓄積する
テストを作れるソフトやアプリには、例えばWordやExcel、今ならGoodNotesなどもあります。私は使ったことはないのですが、教育現場では一太郎というソフトも根強く残っていたりします。
教科によって問題や解答の形式が違うので、使いやすいものを見つけるといいです。
私は、問題用紙はWord、解答用紙はExcelで作っていました。図版などは後から原始的にコピーして切り貼りして調整していました。今やるなら、その部分はiPadでGoodNotesなどを使って貼り付けると思います。
解答用紙の作り方は、エクセルの列を縮めて方眼用紙のようにして、問題に合わせてマスを作っていくようにするとやりやすかったです。
また、作ったテストは、自分のデータとして保存しておきましょう。
すぐに同じ問題を使うことはないにしても、次の年に見返して類題を作ったり、何年後かにプール問題として使用することもできます。
そして、テストは学校のPCで作成するのもいいですが、異動のときにデータを移すのが難しい場合などは、最初から自分のPCで作っておく方がいいと思います。
勤務校のある自治体のデータ取扱いのルールを調べて、作成したデータを自分で保管できるやり方を見つけましょう。
まとめ
テストは教科によって様々です。
自分と同じ教科の先生に試験を見せてもらうのもとても参考になりますが、私はよく自分が試験監督の時に、他の教科の問題用紙や解答用紙も見て、こんなやり方もあるんだなとか思っていました。
ここで書いたことも少しでも参考になれば嬉しいです。