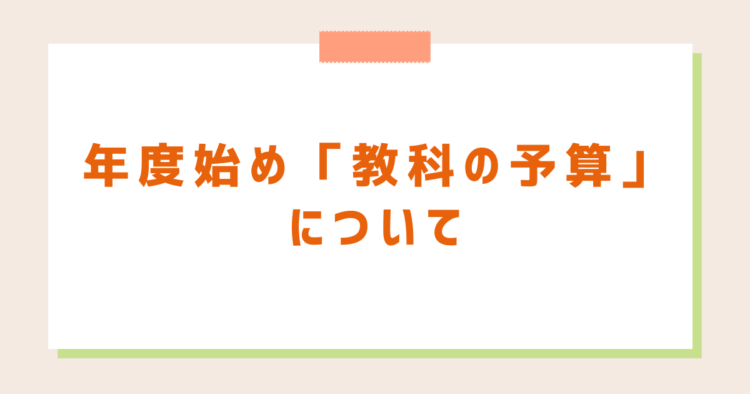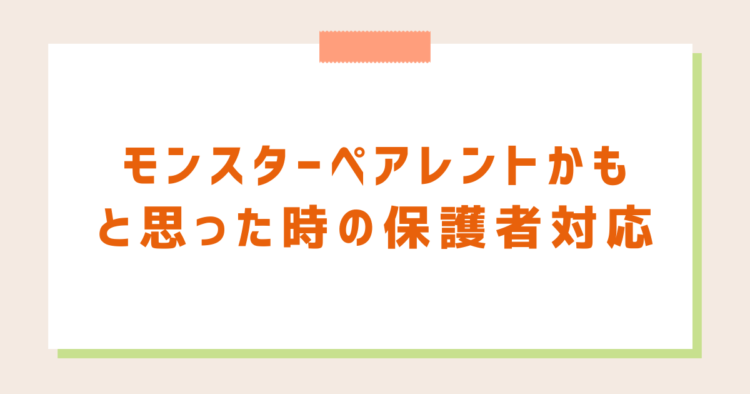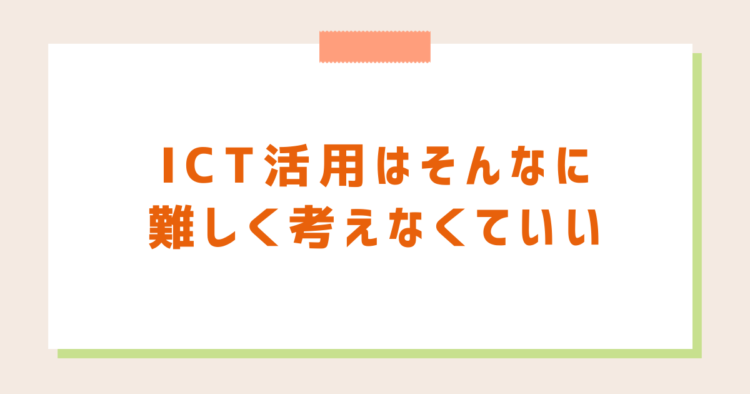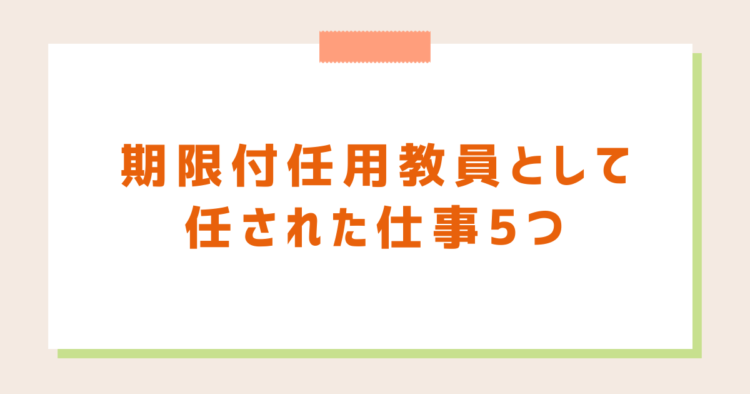家庭科の調理分野の評価方法
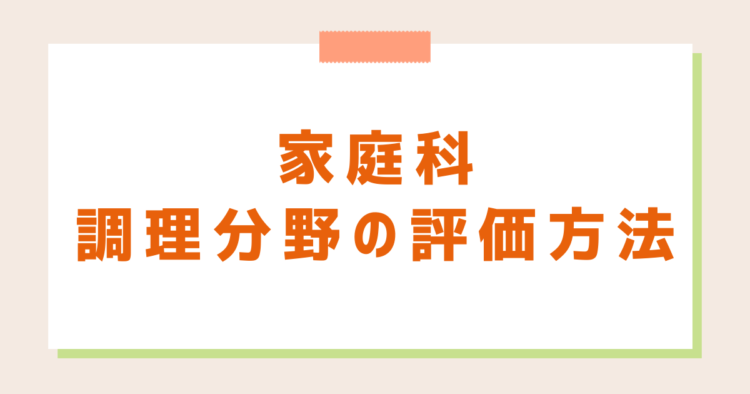
今回は、少しニッチですが、家庭科の先生に向けて、技術点をどのように評価していたか、私なりの方法を書いてみたいと思います。
というのも、調理分野の授業では、だいたい1時間で準備から片付けまでしなければならなかったり、あまりにも時間がタイトで、その中で実技の評価をどうすればいいのか、私自身がとても悩んだからです。
調理実習の内容によって、パターン別に書きます。
実習の内容が少ない場合、その場で評価する
これは、調理と呼べることはほとんどしないくらい、本当に少ない内容の時です。
具体的には、リンゴの皮剥きテストを行いました。
最初の実習で、調理室に慣れるという目的も兼ねていました。りんごを切って、包丁で皮を剥く、それだけの実習です。
包丁で切る時間は、10分くらいあれば十分なので、名簿を持って端から回っていき、その場で評価していきます。
当時の私の評価の内容は、切り方の技術を5段階くらいで評価したのではないかと思います。
もし今また同じようにするなら、評価方法は、もう少し細分化します。
調理台が6つとか決まっていれば、2班ずつなどよーいスタートで切り始めさせ、①包丁の手つき、②リンゴの皮などの廃棄率の少なさ、③出来上がりの綺麗さ、くらいに分けてそれぞれ3点ずつくらいで採点します。
当時は採点の仕方も自己流でしたが、後々、他の先生のお話などをお聞きして、5点〜10点など幅の大きい点数で1項目を採点するより、3点で複数項目に分けた方が、様々な角度から、直感的にどんどん評価することができるということに気づいて、それからはこのようなやり方でやることが増えました。
あくまでも、評価の項目ややり方は、それぞれの先生方のやり方があると思いますので、自分に合ったやりやすい方法を見つけてください。
調理に時間がかかる場合、写真に撮って後から評価する
一般的な調理実習の時は授業中に評価して回るのは不可能に近いです。というのも、こちらで準備した食材を配っていったり、生徒に呼ばれたりなど様々なことに対応が必要だからです。
そこで、事前の授業で、紙にサインペンで名前を書いて名札(といってもただのコピー用紙を切っただけのもの)を作らせておき、当日はその名札とテーブルに1台デジカメを配って、自分の切ったものをその名札と一緒に写真を撮っておいてもらいました。
後から、その写真を見ながら切り方の技術について評価していきます。
また、調理実習の成果物、つまり料理は食べたらなくなりますが、この方法ならある程度は客観的な証拠が残るので、学期末に保護者からの問い合わせなどがあったときにも、提示できるのがいいところです。
態度は実習中に見て評価する
実習内容やその時の余裕によりますが、態度の項目は、実習中にさっと見て、その場で名簿に採点していました。
生徒ごとの動きを見て、積極的に適切に動けているか、印象で評価していくので、それほど時間はかかりません。
もし、余裕があるなら、準備段階と片付けの段階など数回に分けて採点できればいいなと思います。
自己評価シートで意欲を評価する
技術以外にも、意欲や態度も評価する必要があります。
参加賞に近いですが、Yes・Noで答えられる10問くらいの質問に、感想や工夫したことを書かせて提出させていました。
質問は、忘れ物をせず持ち物(エプロン)を準備できた、積極的に片付けをできた、などです。
評価は、基本的にはYes・Noの項目よりも、感想や工夫した点などの記述部分を重視していました。といっても、これも3点満点くらいで採点していたので、これだけでそれほど大きな差は出ません。こういう小さな点数の積み重ねで最終的に差がつくようになっています。
まとめ
実技教科の採点、中でも家庭科の調理実習は、何か作品が残るわけでもなく、何か数値が出るわけでもないので、評価が難しいと感じます。
ポイントは、3点満点など点数を小分けにして複数の項目で評価することと、写真や評価シートなど、客観的に見える「もの」も評価の対象に加えることです。
この記事が、少しでも参考になれば嬉しいです。