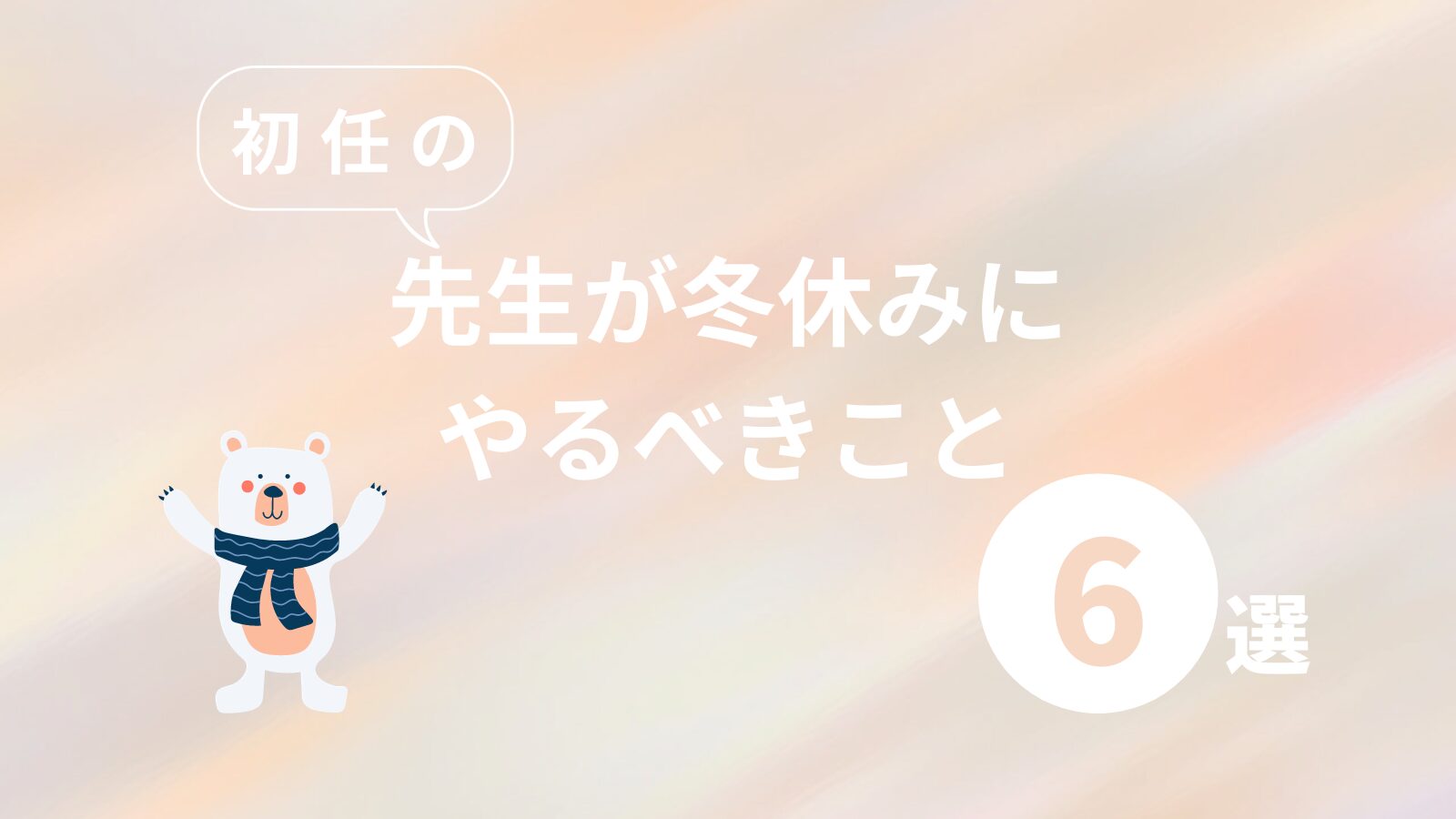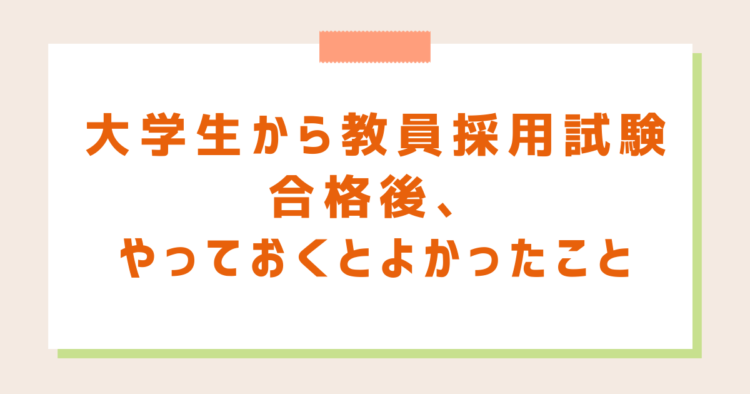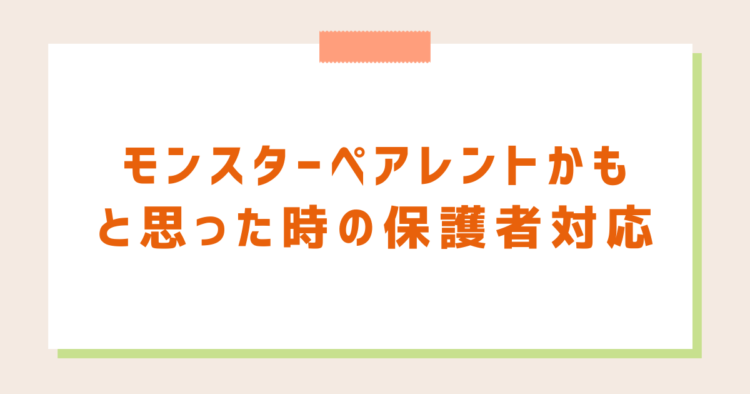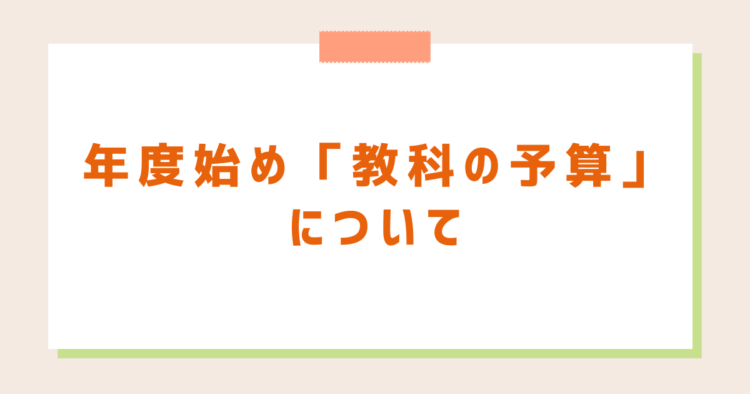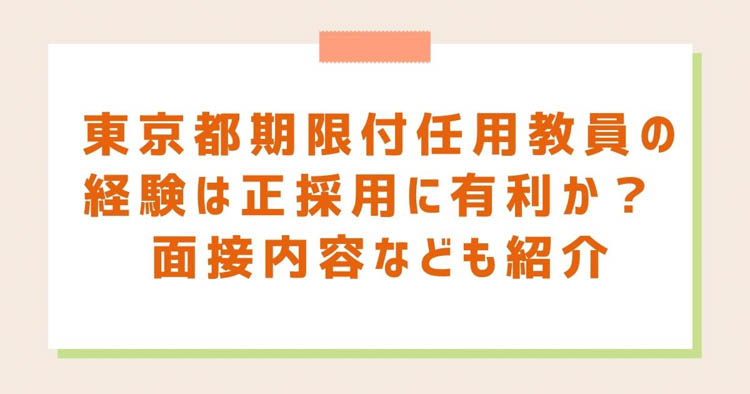真面目になり過ぎてはだめ、手を抜けるところはどこか?
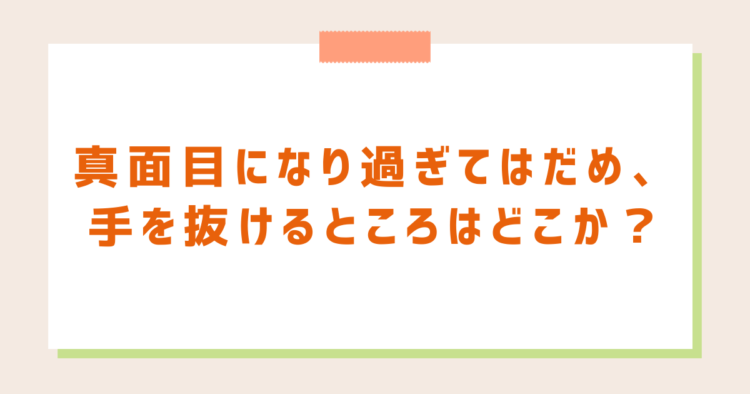
言うまでもなく、先生という仕事は忙しいです。やろうと思えば、仕事は無限にあります。
でも、その仕事をすべてやってはいけません。忙しいからこそ、絶対にやるべき仕事と手を抜けるところを見極めるべきですし、息抜きも必要です。
今回は、4月から先生になるけど、働き方に不安があるという人のために、どうすれば燃え尽きずに仕事ができるのか、私なりのコツや心掛けていたことを書いてみたいと思います。気軽な気持ちで読んでみてください。
どうやったら時給を最大化できるか考える
先生になろうという人は、これまで優等生だったという人が多いです。
優等生というのは、勉強ができることもある程度はあるのですが、それよりも人間的に真面目で、人の言うことを素直に聞いてきた人というイメージです。
教職員には休職者が多いことはニュースにもなっていますが、これは教員という職業が労働時間的に過酷なことに加えて、もともと真面目な方が多く、別にやらなくてもいい仕事まで完璧にしようとする方が多いのではないかと思います。
そこで、おすすめするのは、どうやったらサボれるかという視点で考えるということです。サボるというのはあまり品がないですが、言いたいのは「どうやったら時給を最大化できるか」考えてほしいということです。
この考え方ができるようになると、仕事の優先順位をつけて必ずやらなくてはいけないことからやったり、他の先生のやり方を盗めるところは真似させてもらったり、効率的に仕事ができるようになります。
私は、テストの採点をいかに楽にするかなども考えていました。
最初から早く帰宅するキャラになる
先ほどの時給を最大化するに通じることなのですが、初任の時から、早く帰るキャラとして職員室で認知してもらうことが大事です。
定時でダッシュできれば理想ですが、そこまででなくても、18時すぎ、遅くとも19時には帰っているくらいであれば上出来です。
これの何が大事かというと、精神的に早く帰りやすくなるからです。
教員になる人には真面目な人が多いので、自分の仕事は終わっていても他の人が仕事をしていると帰りにくいという人がいます。その結果、別にやらなくてもいい無限にある仕事をやっていてダラダラ残ってしまうというパターンが多いです。これは本当に意味がないというか、教員全体の悪い文化です。こんな文化を知る前に、クリーンな労働環境を自ら整えるようにしましょう。
また、早く退勤していると結果として仕事ができる人になれます。毎日、タイムリミットを決めることで仕事も早く終わらせようという気持ちで取り組めるからか、周りの先生方を見ていても、結局、早く帰る人の方が仕事ができる人だと感じました。
学校に長く残っていても、睡眠時間が減ってすべての効率が落ちるだけなので、とにかく早く帰って休息しましょう。
やらなくていい仕事はやらない
やらなくていい仕事はやらない、これにつきます。
具体的には、毎日連絡帳を集めて日記に返事を書くこと、教室の装飾をすることなどです。
連絡帳を集めてそれに一言日記を書かせる先生がいますが、そんなことをしていては、どれだけ時間があっても足りません。
また、教室をきれいに装飾というか、掲示物をものすごく丁寧に貼る先生がいますが、個人的にはそれも結局は教員の自己満足に過ぎないと思います。
それでも学年で統一して、学級活動や総合の時間に作った作品を貼らなければいけない場合は、生徒にやってもらうようにしていました。掲示係がいればその子たちにお願いしますし、そのような係がなければ、誰かやってくれる人〜とお願いします。
さらに、クラス全員の掲示物を掲示するときは、出席番号順に並び替えたりせず、バラバラに掲示するようにしていました。これは、並び替えるのが手間というのもありますが、番号順にすれば、不登校などで提出できていない生徒が目立ってしまうためです。
生徒に任せると、味のある芸術的な感じになって、のびのび自由な雰囲気が出るので、個人的にはそういう掲示の方が好きでした。
生徒の安全に関わることは手を抜かない
一方で、生徒の安全に関わるようなことは手を抜かないようにします。
例えば、教室の美化には気をつけるようにしていました。先に書いたように、装飾はしませんが、清潔という意味でのキレイは保てるように心がけていました。
喧嘩が起こったときに武器になるようなものはできるだけ置きたくないし、やはりすっきりした部屋の方が、子どもたちも落ち着くのではないかと思います。
また、保護者への連絡はできるだけこまめに入れるようにしていました。長く不登校で保護者との関係性が作れている場合などは、週1回や2週間に1回など時間を決めて少し間隔が空いて連絡することもありましたが、毎日登校している子どもたちに突発的なことが生じた場合には、とりあえず連絡するようにしていました。
例えば、運動会の練習で転んで口の中を切って保健室に行った場合に、きちんと手当てして大丈夫そうだし放課後には普通にしているし連絡するほどではないかもな、と迷ったときも、足を擦りむいた場合とは少し事情が違うので、放課後に保護者に連絡を入れました。
伝え方は、怪我をした経緯と、保健室で手当したこと、現在は落ち着いているので大丈夫だとは思うがご家庭でも様子を見てほしいこと、もし何かあれば病院を受診してほしいことです。
だいたいの場合は大事には至らないのですが、何かあった時のリスクヘッジになること、この手間をかけることで保護者からの信頼も得られることから、こういうところは手を抜くべきではないと思います。
安全に関わることをしっかりすることで、保護者からのクレームなど、不毛な業務の芽を事前に摘み取ることができます。
有給を程よく消化する
特に中学校の先生だと、部活動の担当があるために、有給を消化できないどころか土日すら出勤していて代休も消化できずに捨てているという場合もあります。
これはもったいないというより、労働環境として悪く、体調面でも心身ともに支障をきたすことになりかねないので、意識的に有給を消化するようにしましょう。
なかなか普段の平日には取りにくいですが、その場合には半日ずつ取ったり、時間単位で最後のコマで有給を取得して放課後にさっと帰るなどの使い方がおすすめです。
また、夏休みなどの長期休暇は積極的に取りましょう。ただし、すべての自治体か定かではありませんが、少なくとも東京都のいくつかの自治体では、コロナ以降、今でも夏休みは在宅ワークということで学校に来なくても出勤扱いにできる場合もあるので、管理職などに聞いてみましょう。
有給は初年度は20日で余った分はすべて次年度に持ち越しができますので、個人的には10日くらい使って、残りを次年度に持ち越すのがいいのかなと思います。もし急な体調不良などがあれば年休を使うことになるので、全ては使い切らない方がいいです。
まとめ
教員の仕事は本当に多いので、ぼーっとしているとあっという間に時間が経ってしまします。
心身の健康を保つためにも、まずは最低限のレベルだけクリアして、時間と気持ちに余裕が出てからできる仕事を増やしていくのがおすすめです。